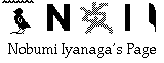
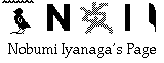
彌永信美
一九六〇年代後半の二年間をぼくはパリで過ごしていた。時代はいうまでもなく、「第三世界」の革命‐解放闘争に呼応して「先進諸国」の学生運動が激しく燃え上がり、また、アメリカ・ウェストコーストから生まれたカウンター・カルチャーの波が世界を覆い始めたころだった。当時、大学都市[シテ・ユニヴェルシテール]方面に向かうパリの地下鉄には、多くの黒人やアラブ人の学生などが乗っていた。たまたまそうして隣の席に乗り合わせた見知らぬアラブ人学生などが、急に身を乗り出して「君も東洋人[オリアンタル]だな、ともに闘おう」と力強い調子で話しかけてきて――そのたびに、ぼくは当惑して曖昧な「ジャパニーズ・スマイル」を浮かべながら「ウイ、ウイ……」と口ごもるほかなかった。
「東洋人[オリエンタル]」であるとはどういうことか。「黄色い白人」の日本人として、また「東洋学[オリエンタリズム]」の一部門である日本学の講義に通う者として、パリで生活するぼくはいったい何者だったのだろうか……。
それから二十年近くして、「オリエンタリズムの系譜」という副題を付した『幻想の東洋』(青土社、一九八七年)という本を書いたのは、いくらかはこの頃の自分自身に対する疑問から発していたのかもしれない。そして、その『幻想の東洋』が書店にならぶ数カ月前に、前から評判の高かったE・サイードの『オリエンタリズム』の邦訳がようやく刊行された【E・サイード著『オリエンタリズム』(今沢紀子訳、板垣雄三・杉田英明監修、平凡社、一九八六年)。原著、初刊・一九七八年。】。拙著の副題に「オリエンタリズム」という語を入れたのは、ひとつには、サイードの著作が出版早々、高い評価を受け、上々の売行きを示していたという理由もあった。
しかし、「オリエンタリズム」という語そのもの、そしてサイードの著作におけるその用法には、最初からある種の抵抗感があったことも告白しておかなければならない。そのことについては、同じ一九八七年に「問題としてのオリエンタリズム」という論稿を書いて自分なりに整理してみた【拙著『歴史という牢獄』〔青土社、一九八八年〕に収録。初出『現代思想』一九八七年七月号〔以下、引用は拙著による〕。】。しかしその後は、日本ではオリエンタリズムに関する議論はほとんどまったく立消えになったままであるように思われる。
そのあとで、「オリエンタリズム」という語が使われているのを聞いたり、読んだりしたことは多くない。が、いま思い出す二つの例は、「オリエンタリズム」概念がどのように用いられるかを典型的に表わしているように思う。その一つは、ちょうど一九八八年だったか、日本でも封切られたベルトルッチ監督の映画『ラスト・エンペラー』についての新聞の批評だった。そこでは、ベルトルッチが描くところの大時代な中国宮廷生活の描写が、「欧米人特有のオリエンタリズム的感覚」に基づいているというふうに書かれていた。――その指摘自身はおそらく正しいかもしれない。が、そのように『ラスト・エンペラー』を「オリエンタリズム」というカテゴリーに入れることで、人はこの映画についてどのような洞察が得られるのだろう。それはむしろ、この映画をたんに「信用ならない」ものとしてと分類するだけであって、映画自身を理解することにはほとんど何の寄与もしないのではないだろうか。第一、オリエンタリズムは「欧米人特有の感覚」にすぎないだろうか。『ラスト・エンペラー』で物語られた「満州国建国」の歴史は、むしろ一九三〇年代の日本に蔓延したのある種のオリエンタリズムの問題に直結したものではなかっただろうか。
「オリエンタリズム」という語の第二の用例として挙げるのは、磯田光一氏による竹内好批判の文章である。ここでは、いまの「日本のオリエンタリズム」の問題性はもちろん忘れられていない。磯田氏は、むしろそのことを直接とり挙げて、このように書いておられる【磯田光一著『左翼がサヨクになるとき』(集英社、一九八六年) p. 176. ――この文章を始めに見つけたのは磯田氏の著作からではなく、それを引用した松田健一氏の論稿の中である。竹内好著『内なる中国』(筑摩叢書、一九八七年)に付された松本健一氏の解説「原像としての中国へ」 p. 226 参照。】。
竹内好のアジア観が、竹内の良心の所産であることは認めるとしても、そのアジア認識の水位は、オリエンタリズムの枠をほとんど破っていないのである。
「竹内好のアジア観」については、前引の論稿で述べたことがあるし【前掲『歴史という牢獄』 p. 47-48.】、ここでも振り返る機会があるかもしれない。しかし、ここで重要なのは、彼の「アジア観」の内容ではない。どんな思想や事象であれ、「オリエンタリズムの枠をほとんど破っていない」と評されれば、それはその一言で「一刀両断」のもとに片づけられ、(少なくとも「批判」が最大限の理解の努力を前提するものである限り)まさに批判にも値しないものとされてしまうのではないだろうか。
ある思想や事象の内容のいかんにかかわらず、その必然性や意味を理解しようとする意欲を一言で断ち切り、特定のカテゴリーの中に「片づけて」しまうような用語があるとすれば、それは「差別用語」以外のなにものでもないだろう。サイードによるオリエンタリズム批判は、本来なによりも、西欧による「オリエント」蔑視、「オリエント(人)」に対する差別を告発し批判するものであるはずだった。その差別批判の道具であるはずの「オリエンタリズム」という語が、そのまま一種の「差別用語」とされてしまっている。考えてみれば、これは多くの反差別の思想が陥るのと同じ陥穽なのかもしれない。人種主義の差別性を批判することが、ただちに「人種主義者」という差別語を生み出すという逆説――(「彼は人種主義者だ」〜「彼は<オリエンタリスト>だ」)。反差別の言説が即「逆差別」を再生産し永続化する、という悪循環から脱するためにも、オリエンタリズム批判の視点は、もう一度鍛え直されなければならないだろう。
日本で一般に受容された「オリエンタリズム」という概念は、ある意味であまりにも「便利」なカテゴリーであり、何でもそこに放り込んでしまえばあとは安住できるような、いわば一種の「思想の塵箱」に張り付けるラベルのような役割を果たしてきた。オリエンタリズムとは、つまりは他人事の問題(つまりは「西欧
日本におけるオリエンタリズムに関する問題意識にこれほど内発性が欠如しているのは、一つには、それが(例によって例のごとく)「輸入思想」だからであり、また、その輸入元の「最大大手」であるサイードの『オリエンタリズム』自身が、オリエンタリズムを「西欧近‐現代」の問題に限定する強い傾向をもっていたからだろう。これを修正し、オリエンタリズム概念をもう一度有効な批判概念として取り戻すためには、サイードのしごとそのものの批判を通じて、オリエンタリズム問題の視点をあらためて措定し直す必要があるのではないだろうか。ぼくの知るかぎり、こうした作業に手をつけたものは、残念ながら先に挙げたぼく自身の論稿(「問題としてのオリエンタリズム」)しかないようである。ここではまず、この論稿との重複を恐れずに、オリエンタリズム概念を定義し直すところから始めなければならない。
*
最近二十年ほどの(サイードをはじめとする)一連のオリエンタリズム批判が始まる以前は、「オリエンタリズム」とは普通、「東洋学」一般を指す語であり、それ以外はせいぜい、十九世紀の西欧美術で、中近東にかぎられた「オリエント」地域を題材に描かれたある種の幻想的な作品を評する語として用いられていた。
サイードは、そのオリエンタリズム概念を大きく拡張して、次のように書いた。――「……オリエンタリズムとは、オリエントを支配し再構成し威圧するための西洋の様式[スタイル]なのである」(サイード著、今沢紀子訳、前掲書 p. 4a)。「オリエンタリズムの本質〔は〕、優越する西洋と劣弱な東洋とのあいだに根深い区別を設けることである……」(同上 p. 42a)。「……オリエンタリズムとは結局、現実についての政治的ヴィジョンなのであり、身うち[ザ・ファミリアー](ヨーロッパ、西方、「我々」)と他人[ザ・ストレンジャー](オリエント、東方、「彼ら」)とのあいだの差異を拡張する構造をもつもの〔である〕」(同上 p. 43b)。――サイードが示すこうした理解には、もちろん異論の余地はない。
たしかに十九−二十世紀にかけてのオリエンタリズム、特に帝国主義的なオリエンタリズムは、基本的にこうしたものとして機能しただろう。しかしもしそうであるなら、「オリエンタリズム」とは西欧的植民地主義の言説とどう違うのだろう。「オリエンタリズムとは……」決してそれだけではなかったし、またもちろん(サイードが強調する)中近東の地域だけを対象に機能したものでもなかった【前引拙稿 p. 25 sq., p. 23-24 参照。】。オリエンタリズムを「われわれ自身」の問題として捉え直すためには、オリエンタリズム概念をあらためて定義し直すところからはじめなければならない。
このオリエンタリズムの新しい定義とは、じつはきわめて単純である。オリエンタリズムとは、すなわち「世界を西洋と東洋に分けて考える考え方」である【同上 p. 44 以下参照。】。――「西洋と東洋は事実存在するではないか」、「もし、オリエンタリズムが『世界を西洋と東洋に分けて考える考え方』であると言うなら、それはひとつの『考え方』、観念ではなく、事実の認定ではないか」という反論を想定して、念のために言っておくならば、奇妙なことに、丸い地球の表面には「南と北」の極は存在するが、「東と西」の極はどこにもない――それゆえ、絶対的な東洋とか絶対的な西洋なるものは、物理的にはどこにも存在しない。「西洋/東洋」という世界の二分法は、決して自然に湧き出したものではなく、ある歴史的な状況のもとに「発明」された文化的産物である。そして、それが歴史的・文化的産物であるなら、どこでいつ、誰によってそのような観念が「発明」され、どのような状況で維持され、また拡められたのか、ということが考察の対象になるはずである。この意味での「オリエンタリズム」の分析は、それゆえ、何よりもまず歴史的な探究でなければならない。
オリエンタリズムを「観念」ではなく、「事実の認定」とする先の考え方では、古来、ユーラシア大陸の東方と西方には、二つの大きな(大きく異なった)「文明」が存在し、互いにある程度接触しながら、大局的にはそれぞれが大きく異なった方向に発展していったという「事実」が挙げられるだろう。しかし、そうした歴史が、いくらかでも信憑性をもった事実として認められるだけの情報(地理的・歴史的知識)が、はじめて体系的に蓄積されたのは、十五−六世紀以降のヨーロッパ以外にありえなかった。ところが、世界を「西方と東方に分けて考える」オリエンタリズム的世界観が成立したのは、それより遥か以前、おそらく帝政時代のローマであり(初出ウェルギリウス『アエネーイス』VIII, 686)、また十一〜二世紀以後のラテン世界(『ロランの歌』XXX, 40)なのである【拙著『幻想の東洋』(青土社、一九八七年) p. 30-32 and n. 3, 6, 8 などを参照。】。もちろん、こうした古い時代には、「オリエント‐東方」として表象された地域が明確にイメージされたわけではない。しかし、オリエンタリズムは、そもそも幻想の体系であり、それゆえその対象となる地域についての知識は、むしろ正確に把握できないようなものである方が自然なのである。
帝政時代のローマと十一〜二世紀以後のラテン世界という二つの時代は、ともにヨーロッパ、あるいはむしろ「西方」(なぜなら少なくともローマ時代には「ヨーロッパ」なる概念はまだ存在していなかったから)が、みずからを「一つの世界」として認識し、しかも他の地域へと拡張していこうとした時代だった。こうした状況が、オリエンタリズム的世界観の成立に不可欠の条件であったと言えるだろう。――いずれにしても、世界を「東洋と西洋」に分ける考え方は西洋で「発明」されたものであり、それゆえ、「オリエントの生まれ故郷はオクシデントにほかならない」のである【同上書 p. 27.】。
世界を「西方と東方に分けて考える」考え方は、もちろん、世界を「自文化」と「異文化」に分けて考える世界の二分法の一つのヴァリエーションにすぎない。自文化/異文化の二分法は、多くの場合は「文明/野蛮」、「中心/周縁」、「浄/不浄」、「真の宗教を信じるもの/異教徒」などの形をとり、「西方/東方」という二分法は、そのなかでもきわめて特殊なものと言うことができる。西欧で、こうした特殊な世界表象が生まれたのは、明らかにユーラシア大陸における西欧の位置という偶然に基づいたものだろう。しかし、「中心/周縁」などの二分法と比べた場合、「西方/東方」の二分法は、最初から特殊な、二重の意味の普遍性を備えていたということに注意しなければならない。
第一に、「西方/東方」の二分法は必然的に相対的なものであり、その基準となる点(「絶対的中央」)は、現実にはどこにも存在しない。つまり、世界のこちら側を「西方」、あちら側を「東方」であると言う者(「オリエンタリズムの主体者」)は、原理的には「西」でも「東」でもない「世界の中央」に立つ者であるはずだが、そのような「世界の中央」は現実にはどこにも存在しない。だから、たとえば日本は普通は「極東」に位置すると言われるが、基準点を変えさえすれば、論理的には「極西」と言ってもいいし、東西のどこにあると言ってもかまわないことになる。
一方、「文明/野蛮」、「中心/周縁」などの二分法は、それ自体に優劣、上下といった価値を含んでいるのに対して、「西方/東方」には、そうした価値は含まれていない。たとえばもし、オリエンタリズムに「武装」されたヨーロッパではなく、中華思想をもった文化(たとえば中国)が世界を制覇していたとしたら、制覇された地域の人々は、みずからを概念の定義上「劣等なもの」である「周縁地域」の人間と看做さざるを得なかっただろうし、そのことに対する抵抗も、より大きかったと想像できるだろう。
換言すれば、「中心/周縁」的な世界表象によるなら、世界は理想的には「中心」だけによって成り立つべきであり、現実に「周縁」が存在するかぎりにおいて、「中心」が「周縁」を制覇し、「中心化」することによって構成されると考えられるが、「西方/東方」の二分法によるなら、少なくとも論理的には、世界は「西」と「東」という二つの極=対立項を前提し、その両側の主体的な意志によってダイナミックに融合されることによって、はじめて一つの全体=「世界」として成立する、と考えられるだろう。オリエンタリズムとは、いうならば、ある種の弁証法的な「世界」創出の論理なのである。
西欧によって生み出されたオリエンタリズムは、また、西欧による異文化表象の形態、つまりは「エクゾティシズムの西欧的形態」であると言うこともできる。別の言い方をするなら、これは西欧的な他者表象の重要な局面の一つでもある。どの文化においても、エクゾティシズムは「憧憬と恐怖」の両方を伴った、きわめてアンビヴァレントな幻想体系であるに違いない。しかし、西欧的エクゾティシズムであるオリエンタリズムには、西欧文化――それは基本的に「ギリシア哲学とキリスト教(およびローマ法?)」の混合から生まれたと言って間違いないだろう――に特有のいくつかの特徴がある。その最たるものは、空間的「遠方」が時間的過去、または未来と密接に組み合わされていることだと言えるだろう。つまり、人は遠くに行けば行くほど、過去に遡り、あるいは未来を瞥見するのである。
あるいは、オリエンタリズムは一種の「極の思想」であると言ってもいいかもしれない。オリエンタリズムにとって「極東」は世界の始原、または(場合によっては)世界の終末に対応する。この「始原」や「終末」の価値は場合によって逆転しうる。つまり、歴史が進歩するものであるとするなら、「始原」は「野蛮」であり、「終末」は「文明の極致」であるだろうが、逆に退歩的歴史観によるならば、「始原」は「原初の真理」に対応し、「終末」は「終末の混乱」に対応することになる。実際には、ヨーロッパ文化では十八世紀頃まではむしろ退歩的歴史観が主流であって、そのコンテクストではオリエンタリズムはいわゆるプリミティヴィズムに結びつくことが多い。失楽園以前の「アダムの智慧」=絶対的な原初の真理を探究する者は、アダムが住んだという「東方のエデンの園」を探究する者でもある。この種の思考のパターンは、多くの場合、こんにち「原理主義[ファンダマンタリズム]」と呼ばれるような考え方と近い関係にある。また、こうしたプリミティヴィズム的・原理主義的なオリエンタリズムが、世界の中に「隠された絶対的真理」を求めようとするオカルト神秘主義的な傾向を伴いやすいことも容易に理解できるだろう。
いずれにしても、西欧人にとっての西欧の時間は「今」であり、それは一般に、「どちらかと言うと終末に近い現在」として表象される。というのは、この「時‐空間的オリエンタリズム」は、多くの場合「東から西へ」と進む太陽の表象に密接にかかわるからである(ラテン語の oriens は「起きる、現われる」を意味する動詞 orior の派生語で「日の出の太陽」を原義とし、occidens は「落ちる」を意味する動詞 occido から派生して「日没の太陽」を原義とすることを思い出しておこう)。
世界の全歴史は、いわば「東に上って西に沈む」太陽の一日の運行によって暗喩される(たとえば、十二世紀のサン‐ヴィクトールのフーゴーはこう書く。「神の摂理によって、時の始めに起こることは〔天地創造の時に『地上の楽園』が東に造られたのと同じく〕東に起こり、時が終りに向かって過ぎて行くとともに、ものごとの頂点は西へと移りゆくべく定められているもののようである」【『幻想の東洋』 p. 145 参照。――この「世界の歴史は東から西へと進む」という観念は、『ダニエル書』の預言に基づき、古代末期のキリスト教神学の中で成立した。同上書、p. 135-137 and n. 12 参照。】)。この場合は、歴史の始原は当然「東方」に位置し、(文明の)太陽は今、西の中天、または西の地平線近くにあるもの、と考えられる。しかし、この太陽シンボリズムによる世界史の暗喩は、必ずしも最後まで一貫するわけではない。たとえば、このようにして世界史の中心が「西方」に移った今、永く忘れ去られていた「東方」が「西方」によって再び発見される時が近づいている。そして、「東方」がこうしてあらためて見い出されたあかつきには(すなわち、キリスト教的な文脈では、全世界に「唯一の真理」=福音がいきわたり、全異教徒がキリスト教に改宗して、イエス・キリストが「遂に一つの〔羊の〕群のひとりの牧者[ひつじかい]となった」〔『ヨハネ伝』X, 16〕あかつきには)、「世界の円環」が完成し、その時、世界は絶対的な終りに至るのである……。こうした場合には、一種の「円環的時‐空間」のシンボリズムが、自然的な太陽シンボリズムを補完する役目を果していたと考えることができる。
十六世紀頃までに完成するこうした幻想体系としてのオリエンタリズムは、基本的にキリスト教的な普遍主義と歴史神学(終末論)の産物であると言えるだろう。たとえば、十三世紀、モンゴルの大軍が「タルタルスの国より悪魔[サタン]のように襲来して」ヨーロッパを襲ったとき、ヨーロッパの人々は、このモンゴル軍を『エゼキエル書』や『黙示録』に語られた終末の民「ゴグとマゴグ」、あるいは「イスラエルの失われた十の支族」に同定し、人々の傲りを罰するために神意によって「東から到来する世界の終末の民」のイメージが彼らを戦慄させたのだった【拙稿「終末の見える沙漠」、『歴史という牢獄』所収 p. 223-230 ; 『幻想の東洋』 p. 452-454, 第九章・注 6 を参照。】。
一方、クリストーバル・コロン(コロンブス)は、フランチェスコ会厳修派のヨアキム主義的終末論を堅く信じており、みずから「発見」した南アメリカ北部・ベネズエラ東沿岸のパリア湾に「世界一美しい土地」を見い出して、そこが『創世記』に語られた「地上の楽園」(「東方のエデンの園」)に違いない――あるいは少なくとも、人が近づきうるその最短距離にまで到達したと確信した(コロンは、いうまでもなく、彼の「発見」した「新世界」が「世界の極東」に位置するものと信じていた)。なぜなら、彼は「世界の終り」=キリストの再臨が百五十五年後に迫っていることを複雑な計算によって割り出しており、そのときまでに全世界が発見され、全人類が「真の宗教」に改宗しなければならないことを信じていたからである。コロン自身は、こうした「神の計画」の実現に寄与すべく、神によってその使命を定められた一人のしもべにほかならなかった……【『幻想の東洋』第十一章参照。】。
あるいはまた、一五四九年一月、マラッカでフランシスコ・ザビエルと出会った日本人ヤジロウの口述に基づいた、ヨーロッパで最初の「日本事情報告書」がローマに送られると、それを読んだフランスの神秘家ギヨーム・ポステルは、ヤジロウの語る日本の宗教の中に真正のキリスト教が隠されていることを読み取り、その宗教の「シアカ」と呼ばれる教祖が、イエス・キリストその人にほかならないことを確信した。なぜなら、「世の終りがまさに到来するこの時にあって、神は、その御名と教義、儀式が『名ばかり』のものとなって残されている西の果ての民に、御名は忘れられても、生活そのものの中にその真実の教えが生きつづけている東の果ての民を、模範として示し給うた〔から〕である。『かくのごとくに彼らを配[あしら]うこと』が、神の測り知れない御意志だったのであり、それを読み解くことが、『第二のアダム』たるポステルに、永遠の昔から定められた使命だったのである」【同上第十六章、および p. 356.】。
こうした例でも明らかな通り、中世以来のオリエンタリズムは、多くの場合、人間の歴史を「神意の発現の形態」と見るキリスト教的な歴史観の重要な一要素として機能したと考えることができる。オリエンタリズムの言説は、何よりもまず、世界の歴史に「神の計画」、神が世界に定め給うた目的=終末がいかに隠され/顕われているかを読み取ろうとする目的論的解釈学の一環として発展していったのである。
十五世紀末以来、徐々に現実の「東洋」(彼らが「東洋」と呼んだ地域)を「発見」し、「東洋人」との接触の中でさまざまな経験を重ねていくことによって、西欧人のこのような「東洋観[オリエンタリズム]」は当然変化していった。そうした変化の中でもっとも重要なものの一つは、いわゆる「東洋学」の発生と展開だと言えるだろう。東洋を「客体」として研究し、眺める視線がここではじめて生まれてきたと考えられるからである。――とは言っても、少なくとも初期に限って言えば、「東洋学」の主な動機は聖書学の要請であり、またキリスト教宣教のための学であったことも忘れてはならない。ヨーロッパの学者たちは、「東洋」そのものを「客観的」に知り、あるいは評価することを目的に東洋を研究したというより、むしろみずからの宗教の聖典である聖書についてできるかぎり正確な知識を得、あるいは聖書の教えをできるだけ効率的に「異教徒」に拡めるために、東洋について学んだのである。初期の東洋学は、もう一つの「神意の顕現」の形態である聖書を読み解くための補助学として、また、全人類の改宗という、キリスト教徒に課せられた優れて終末論的な使命を実現するための補助学として、発展したと考えなければならない。
十八世紀後半頃からヨーロッパが帝国主義的に拡張していった時代に、オリエンタリズムの内容がさらに変化したのも、もちろん予期できることである。サイードの『オリエンタリズム』は、おもにこの時代以降のヨーロッパにおけるオリエンタリズムの展開について述べ、それがいかに「優越する西洋と劣弱な東洋とのあいだに根深い区別を設ける」役割を果たしたかを強調した。しかし、こうした「差別的オリエンタリズム」の傾向は、ある意味では、抑圧者が被抑圧者に対するときにほとんど不可避的に作動する自己正当化のプロセス――そこでは自己の罪悪感を隠蔽するために、みずからを優越者とし、相手を劣等者とするあらゆる言説が動員される――の中から生まれるもので、必ずしもヨーロッパに特有なものではないし、オリエンタリズムの本質的・特徴的な側面であるとも言い難いように思われる。
このことはまた、サイードがアラブ‐イスラーム世界に対する「差別的オリエンタリズム」に焦点を合わせたことともかかわっている。というのは、アラブ世界は地理的にもヨーロッパに隣接しており、また歴史的にも中世以来、キリスト教世界と密接に関係し、互いに対抗し合いながら発展してきた地域であって、それゆえにヨーロッパの対アラブ感情は、他の「遠い東洋」に対するのとは違う特殊な内容を含んでいるからである。アラブ‐イスラーム世界に対する「オリエンタリズム」は、「世界表象としてのオリエンタリズム」というよりも、むしろ特殊な歴史的状況によって作り上げられたものであり、その意味では、ヨーロッパ内部における反ユダヤ感情にも近いと言うべきである(サイードは、反アラブ感情としてのアンティ・セミティズムに関して多く述べているが、反ユダヤ主義としてのアンティ・セミティズムについてはほとんど一言も言及していない。しかし一般にはアンティ・セミティズムという語は、ヨーロッパ内部の反ユダヤ主義を指して言うことばではなかっただろうか……)。
近代の歴史の中でオリエンタリズムが新しい相を示すようになるのは当然のことだが、ある意味でそれ以上に興味深く、かつ重要なのは、中世以来のオリエンタリズムの伝統的思考が、近代においても驚くべき一貫性をもって保ちつづけられたことである。そうした意味での近代オリエンタリズムの頂点は、ヘーゲルの歴史哲学によって窮められたと言うことができるだろう。おそらくヘーゲルは、地球上の「東と西」が相対的であることを明確に意識しながら、なおかつ「世界史の中には絶対的な東と西」があることを明言した最初の人物である。ヘーゲルこそは、近代の「絶対的オリエンタリズム」を代表する最大の思想家であり、それゆえその思索の跡をたどることは、「われわれ自身の問題としてのオリエンタリズム」を考えるために不可欠の作業だと思われる。
ヘーゲルにとっての「東と西」の問題を考える以前に見ておかなければならないのは、彼の『歴史哲学』の基本構想そのものである。ヘーゲルの歴史哲学は、彼自身のことばによるなら、「理性が世界を支配するということ、したがって世界史においてもまた一切は理性的に行なわれて来たという、単純な理性の思想である」【ヘーゲル著、武市健人訳『歴史哲学』(岩波文庫、一九七一年)、上 p. 65.】。そこで言う「理性」、あるいは「精神の実体、本質〔が、物質の実体が重力であるのに対して〕自由である」とすれば (p. 76)、「世界史とは〔要するに〕自由の意識の進歩を意味する」のであり (p. 79)、あるいは世界史の究極的な目的は「自由〔が〕自分を意識し、〔……〕それによって自分を実現する」ことであるという (p. 80)。こうした完全に目的論的な歴史観は、当然、キリスト教の歴史神学と密接に関係したものと考えられるだろう。事実、『歴史哲学』の序論には、この歴史神学の中心理念である「摂理」(providentia)の概念とヘーゲル自身の歴史哲学とのかかわりについて述べた箇所がある。ヘーゲルによれば、
〔……〕神の摂理が世界の諸々の出来事を支配するという真理は、上述の原理〔理性が世界を支配するという原理〕と対応する。なぜなら、神の摂理とは、その目的、すなわち世界の絶対的な、理性的な究極目的を実現するところの無限の力という面から見た知恵であるが、理性は全く自由に自分自身を規定するところの思惟だからである。〔……しかし〕この〔神の摂理への〕信仰もまた〔……〕漠然としたものであり、〔……〕全体への適用、すなわち世界史の全行程への適用となるというところまでは行かない。しかし、歴史を説明するということは、人間の情熱、その天才、その活動の力を明らかにすることを意味する。そしてこのような摂理の規定性〔実現過程〕は通常、摂理の計画と呼ばれる。けれども、この計画は、われわれの眼には隠されているとせられ、これを認識しようとすることさえ僣越だとせられている。〔……〕というのは、人々が摂理の存在を認めるのは、たまたま特殊の場合だけであって、それは敬虔な心の人が個々の突発的な事故の中に偶然をではなくて、神意を見るような場合にすぎないからである。〔……〕しかし、このような目的は、それ自身限られた、狭い範囲のものであり、単に一個人の特殊な目的にすぎない。ところが、われわれが世界史において問題とするのは、民族という個人であり、国家という全体である。だから、われわれはそんな摂理の信仰のいわば小売商とでもいったものを相手にしているわけにはいかない。〔……〕われわれはむしろ本気に、歴史の中における摂理の道程、その諸々の手段、その諸々の現象を認識することを問題にしなければならず〔この部分の傍点・引用者(ただし、以下、特に断らないかぎり傍点は原文による)〕、これを上述の一般的原理に関係づけることを問題にしなければならないのである(同上 p. 69-71)。
つまり、ヘーゲルにとって、摂理の概念――すなわちキリスト教的歴史神学の原理――が物足りないと思われるのは、たんにそれが不徹底にしか適用されないからであって、彼の歴史哲学とは、簡単に言うならば歴史神学の徹底化であり、人間の全歴史を「神意の顕現であり、その展開の形態」として解釈する歴史神学を、いわば「文字通り」(「本気に」)現実の歴史に当てはめて考えようとした試みである、と言うことができる。
事実、ヘーゲルによれば、「自由がそれ自身を意識し、それを実現するという目的は、〔……〕精神の唯一の目的であり、」
この究極目的は世界史の営みの目標となったのであり、地上の宏大な祭壇の上で、また長い時間の経過の中で、この目的の前にあらゆる犠牲が捧げられたものである。〔……〕またこの究極目的は、神が世界に求めるその目的である。しかし、神は最も完全なものであるから、自分自身以外、神自身の意志以外の何ものをも意欲することはない。ところが、神の意志の本性〔……は〕、すなわち、われわれがここに自由の理念と呼んでいるものにほかならない(p. 80)
のである。「神の意志の本性」が「自由の理念」であり、「世界史の究極目的」がすべて「自由がそれ自身を実現すること」であるのなら、つまり世界史の目的とは、神の意志の実現以外のものではありえない。――それゆえヘーゲルは、彼の歴史哲学の構想全体を指して、それはある意味では「神義論」である、と言うことができる (p. 73)。なるほど、ある種の穏健な神学においては、神の絶対性を強調するために、人間は神を認識することはできないと言い (p. 71)、人間の理性が「神の計画」を読み取ろうとすること自体が「僣越である」と主張するかもしれない。また、言語の日常的な用法では、「摂理」という語は「例えば、或る個人が逆境に立ち、苦難に悩むとき、思いがけなく救いの手が現れるというような〔特殊な、個人的な〕場合」(p. 70) に、「天佑」、「僥倖」というような意味で用いられるかもしれない。
しかし、古代イスラエルの預言者の時代以来、ユダヤ‐キリスト教の伝統においては、世界の歴史はつねに神と人間との間に繰り拡げられるドラマと考えられたのであり、歴史上の大事件は、すべて「神意の顕現」として解釈された(たとえば一〇九五年、教皇ウルバヌス二世の、第一回十字軍の蹶起の呼びかけの演説に集まった人々は、口々に「神がそれを望み給う」と叫んだという……【『幻想の東洋』 p. 17 and n. 21 ; p. 160-162 参照。】)。ヘーゲルの歴史哲学とは、ある意味では、まさに、この「神意の顕現」としての歴史解釈学にほかならない。一部の「穏健」な、不可知論的な神学の傾向に対して、ヘーゲルはいわば「過激な歴史神学」を志向し、そのことによって中世的な神学の伝統を復活させたと考えることもできる。その意味では、ヘーゲルの歴史哲学は、近代――「理性の時代」――に甦った第二のアウグスティーヌスの『神の国』Civitas Dei である、と言ってもいいだろう。
この Civitas Dei という題名が「神国」とも訳されうること、そしてその同じ「神国」という語が、近‐現代の日本の歴史の中で、ある驚くべき野蛮な精神の標語として機能したこと、そのことを考え併せれば、以下のページで語ろうとしていることの大半が理解されるだろう……。
さて、このような枠組の中で、ヘーゲルは「東と西」についてどのように考えていただろう。――『歴史哲学』序論には、ヘーゲルが伝統的な「退歩史観」的、プリミティヴィズム的・「原理主義」的かつオカルト神秘主義的なオリエンタリズムの言説を熟知していたことをうかがわせる箇所がいくつかある(同上 p. 142-147 ; p. 149-150 ; p. 155-156 ; p. 161-164 など)。たとえば、ヘーゲルは「原初の人間アダム」に関説して、「また自然は、そのはじめには、神の創造の明澄な鏡のように、あらわに、透明に (offen und durchsichtig) 人間の澄み切った眼の前に立ち現われていたし、また神の真理も同様に、その人間の眼にはあらわであった」という説を引いてドイツ・ロマン主義の最大の旗手フリードリッヒ・シュレーゲルを引用し、さらにそうした説の根拠として構想された「古代アジアの諸事情、神話、宗教、歴史に関して昔から記録として残っている宝庫の新たな研究」についても言及している。
ここで彼が名前を挙げているラムネ師や、ルイ‐クロード・ド・サン‐マルタン、あるいはエックシュタイン(エクスタン)男爵などは、(ヨーロッパにおける最初期のサンスクリット研究にも深くかかわったF・シュレーゲルとともに)十八世紀末から十九世紀初頭の西欧における「プリミティヴィズム的・『原理主義』的かつオカルト神秘主義的な」(カトリックの)反動思想家の代表者であって、当時の一般的な「東洋学」の教養がどういうものであったかを示すものとして興味深い【同上 p. 142-145 ; および R. Schwab, La Renaissance Orientale, Paris, Payot, 1950 参照。】。
しかし、こうしたカトリック的・フランス的(?)な退歩史観に基づいた「古代〜東方礼賛」の言辞は、ヘーゲルによって単なる「こじつけ」であり、「大小様々な事実の勝手な屁理屈による組み合せ」であるとして、一言のもとに片づけられてしまう(同上 p. 142, 147)。ヘーゲル自身は、いうまでもなく「理性的」な進歩史観論者であり、それゆえ歴史は<精神の幼児期である東方>から始められなければならない。とは言っても、実は、退歩史観を唱える反動主義者も、「理性の進歩」を確信するヘーゲルにとっても、「歴史がア・プリオリに東方に始まる」ことに関しては何の違いもない。彼らは明らかに同じ「エピステーメー」に属する者として思考しているのである。
ただ、「歴史が東方に始まり、西方に終る」という原則には、ヘーゲルは最初からアフリカとアメリカという例外をもうけなければならない。アフリカは、ヘーゲルによれば「歴史をさかのぼりはじめるや否や、もう他の世界との関連が断たれている。それは自分の中に閉じこもっている黄金の国であり、自意識をもった歴史の真昼の彼方で夜の帷[とばり]に包まれているお伽話の国である」。「アフリカの場合には、われわれの場合に見られるような、すべての観念に通ずる原理、すなわち一般性のカテゴリーは全く断念しなければならない〔……〕。黒人[ネグロ]の特徴は、彼らの意識がまだ一向にチャンとした客観性の観念、例えば神とか法律などというようなものの観念に達していない点にある」。「〔……〕以上に述べた例から明らかになることは、黒人の性格が自制の欠如という一語につきるということである。しかも、この状態は啓発と、教化の不可能なものであり、その見込みのないものである」。それゆえ、ヘーゲルは「アフリカの考察はこれでやめるが、また後にも、もはやそれについて述べることはしないつもりである。というのは、アフリカは歴史的世界には属せず、したがってそこには運動と発展は見出されないからである」と書いて、アフリカを世界史の舞台から完全に消し去っている(同上 p. 198 ; p. 200 ; p. 209-210)。
一方のアメリカ(「新世界」)に関しては、考え方はまったく逆である。メキシコやペルーなどについて報告された記述によれば、「これらの国の文化〔は〕全く自然的なもので、精神がそれに近づくや否や、直ちに消滅するといった種類のものであることが分かる」(ここで言う「精神」とはいうまでもなく「西欧社会」のことである!)。それゆえ、アメリカ原住民の世界は、ほとんどアフリカほども顧慮に値しない。実際に、アメリカに<歴史の名に値するような歴史>があるとすれば、それはすべて、西欧の人々が原住民の世界を「消滅」させた以後のことであり、したがって、「ここで今まで起こったことは旧世界の反響にすぎ〔……〕なかった」。
「アメリカは、それ故に未来の国である。そこでは将来の時代において、例えば南北アメリカの抗争といったような形で、その世界史的な意義が示されることであろう。〔……〕ともかく、アメリカは今日まで世界史の行なわれて来た地盤からは除外しなければならない」(傍点・引用者。――同上 p. 181 ; 189-190)。ここで、「ともかく」と書いたのは、ヘーゲルにとって苦しいところだっただろう。アメリカが「未来の国」であると言われるのは、「世界史は東から西へ」進むという大前提に基づいているからである(アメリカの「未来性」については後述も参照)。にもかかわらず、ヘーゲルにとって、歴史の終末は(彼の時代の)「現代のゲルマン世界」においてすでに到来していると考えられている。それゆえに、世界史は実際には西ヨーロッパより西に「進む」ことはありえないのであり、アメリカが「未来の国」であると言っても、その「未来」はヘーゲルの歴史哲学から見れば、ほとんど現実的な意味をもっていない。だからこそ、「ともかく」アメリカは彼の考察からは「除外視」されなければならないのである。
さて、以上のようなコンテクストを頭におけば、ヘーゲルが「世界史の東と西」について次のように書くことも、容易に理解できるだろう。――彼は、先の「アフリカについての考察」を終えた後、こんなふうに書き始める。
そこで、今このアフリカを後にするときはじめて、われわれは世界史の真の舞台に上る。しかし、ここにはまだアジアとヨーロッパとの地理的基礎について前以って述べておく仕事が残っている。アジア〔傍点・原文〕の世界における位置は一般に、それが「日の出」の世界だということである。なるほど、アジアはアメリカから見れば西に位する。しかし、ヨーロッパが一般に旧世界の中心であり、また終局であって、そのかぎり絶対的に西方であるという点から見ると、アジアは絶対的に東方である。
精神の光と、したがってまた世界史とはアジアにはじまった(傍点・引用者。――同上 p. 211)
とはいっても、東アジア世界は、まだ世界史の黎明にすぎない――。
広大な東方アジアは世界史の行程からは離れていて、それには与[あず]からない。同様に北方のヨーロッパも、後になってはじめて世界史の中に顔を出すのであって、古代にあっては世界史には与からなかった。というのは、古代においては世界史は全然、地中海の周囲に位する国々に限られていたからである。ユリウス・カエサルのアルプス越え、すなわちガリアの征服と、これによって開かれたゲルマン人とローマ帝国との関係とは、世界史に一時期を劃したものであった。というのは、ここに世界史はアルプスを越えることになったからである。東方アジアとアルプス以北の地方とは、この地中海を囲んで動いていた中心の両極〔両項〕である。――それは世界史の始めと終り、その日出と日没とである。(同上 p. 191-192)
こうして、「日出から日没へ」と譬えられた「世界史の哲学」の大前提が言明される――。
世界史は東から西に向かって進む。というのは、ヨーロッパこそ実に世界史の終結であり、アジアはその端初だからである。東方ということはそれ自身としては全く相対的なものであるが、世界史にとっては絶対的な意味での東方 (ein Osten, kat'exochen) が存在する〔傍点・引用者〕。というのは、地球は球体をなしているにかかわらず、歴史は地球の周りを円環を描いて廻るものではなく、むしろ歴史は一定の東方をもつものであり、この東方がアジアだからである。外なる自然の太陽もここから昇り、西に没する。しかしその代りに、自意識という内なる太陽は西に立ち現われて、それよりもずっと輝かしい光を放つ。世界史は自制のない自然的な意志を普遍的なものと主観的自由とに訓育するものである。東洋はただ一人の者が自由であることを知っていたのみであり、また今も依然としてそうである。これに反してギリシアとローマの世界は若干の者が自由であることを、ゲルマンの世界はすべての者が自由であることを知っている。したがって、われわれが世界史において見るところの第一の形態は専制政体 (Despotisumus) であり、第二の形態は民主政体 (Demokratie) と貴族政体 (Aristokratie) であり、第三の形態は君主政体 (Monarchie) である(同上 p. 218. ――『幻想の東洋』 p. 145-149 も参照)
こうして見てくれば、ヘーゲルの歴史哲学が、いかに深く神話的、または「中世的」なア・プリオリに基づいて構成されたものかが理解されるだろう。中世的な歴史神学の延長線上に置いたとき、始めてヘーゲルの歴史哲学と、そこに含意されたオリエンタリズムが、一つの必然として現われてくるのである。
しかし、その同じ延長線上には同時に、サイードが批判したような、いかにも「近代的な」オリエンタリズムの言説も読むことができる。たとえば、彼はアジア世界を「シナと蒙古、インド、ペルシャ、エジプト」の四つに分割して、それぞれについて概観した中で次のように書いている。「シナでは君主が族長として天子である。したがって、国法も一面からいえば法律的であるが、また一面からいえば道徳的である。その結果、内面的な法則、いいかえると主観自身の内面性としての主観の意志の内容についての主観の知識も、それ自身外面的な法律命令として存在することになる。だから、内面性の領域は、ここではまだ成熟の域には達していない」。一方、インドでは、「〔……〕ちょっと見ると個人は差別から解放されているかのようにも思われるが、やはり個人の自立はない。〔……〕そこで、〔抽象的な一者、すなわち単純な神の観念と、全く感覚的な自然力の観念との〕関連は絶えざる転換ということになり、〔……〕清浄な、分別ある人の意識には乱心としか思われないような、野蛮な、わけのわからない迷信[タウメル]〔難行やまた一般の迷信〕が横行することになるのである」(同上、p. 233-234)。
さて、ヘーゲルによると「このシナの運動のない一者と、インドの流浪的な、統一のない不安定とに対して現われる第三の偉大な形態はペルシアである〔傍点・原文〕。シナは全く本来の意味で東洋的であるが〔傍点・引用者〕、インドはギリシャに対比され、これに対してペルシアはローマに対比されることができるだろう……」という(同上 p. 232-234)。
これはもちろん、「文明は極東において最も未熟であり、西に向かうとともに成熟の度を加えていく」という原則にしたがった言明である。しかし、ここで注目すべきなのは、こうした「東洋的」(「本来の意味で東洋的である……」)という語の用法が、まさに本質規定的であり、類型的であり、最も典型的に「オリエンタリズム的」であるということである。
その「東洋的」と言われる内容が何であるかは、基本的に問題ではない。ヘーゲル式に、それが幼稚さや停滞を表わすものとしてある種の蔑視の対象とされるか、あるいはシュレーゲル風に「原初の透明なる真理」を表象するものとして称揚の対象とされるかにかかわらず、こうして本質規定された「オリエントなるもの」は、現実とも、現実の歴史ともいっさい無関係の理念であり、抽象である。もちろん、理念を操り、抽象を思念すること自体に問題があるわけではない。しかし、いっさいの現実が――現実に生きている個々の具体的人間やその生活が、そうした理念や抽象のために「地上の宏大な祭壇の上で、犠牲となって捧げられる」としたら、それは恐るべき倒錯であると言わなければならない。「オリエント」と呼ばれる大地を幻想の祭壇とし、その上で生きた現実を犠牲として屠っていく――、そのような装置としての「オリエント」の幻想は、ヘーゲルにおいてその一つの最も完成した姿を見せているのである。
This page was last built with Frontier on a Macintosh on Wed, Sep 10, 1997 at 19:29:21. Thanks for checking it out! Nobumi Iyanaga